麻雀における食い下がりの意味とは?点数の変わる役も紹介
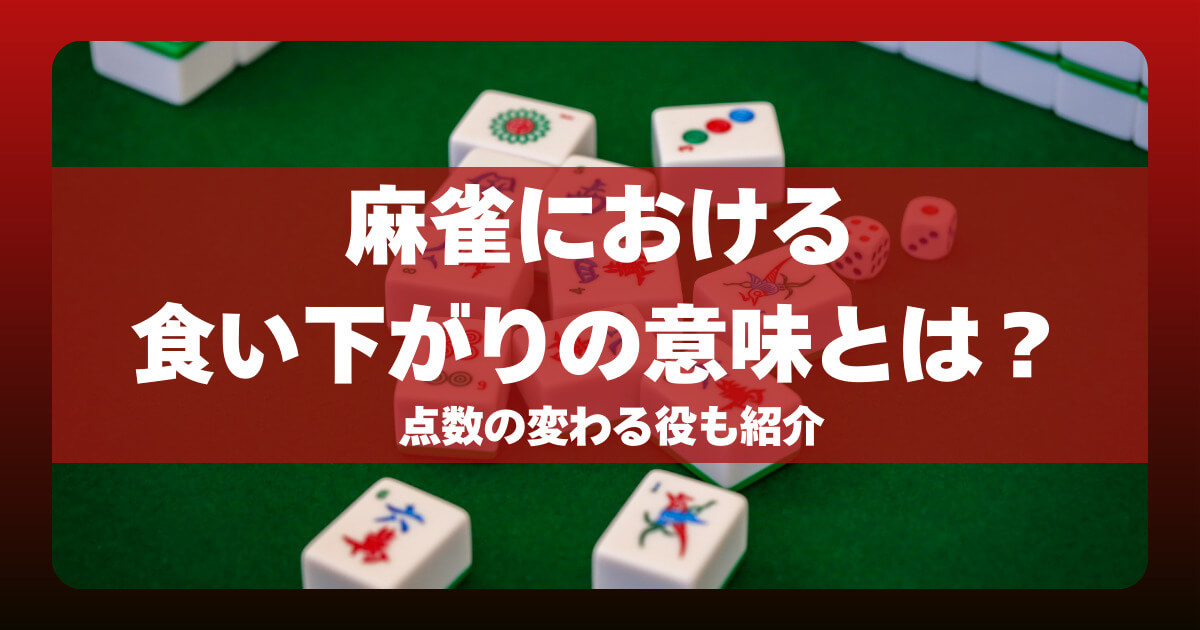
普段から使われている麻雀用語のなかに、「食い下がり」という言葉がありますが、これは麻雀内で起きる鳴き(副露)の際に関係してくる用語です。
麻雀初心者だと食い下がりの意味や使いどころがわからないという方もたくさんいたり、人によってはスポーツで使われている食い下がると同じ意味に捉えている方もいます。
今回の記事では、気になる用語のひとつである「食い下がり」について紹介します。
食い下がりが使われるのはどういう場面なのか、麻雀の試合そのものにどのように影響してくるのかまでを、初心者向けに解説します。
食い下がりの意味が気になる方や、麻雀を始める前に食い下がりについて理解しておきたい方など、気になる方はぜひ一読ください。
本記事は、以下のような内容でお届けします。
- ・麻雀における食い下がりとは
- ・食い下がりになってしまう条件
- ・食い下がりになってしまう役・ならない役
麻雀における食い下がりは鳴きが関係している
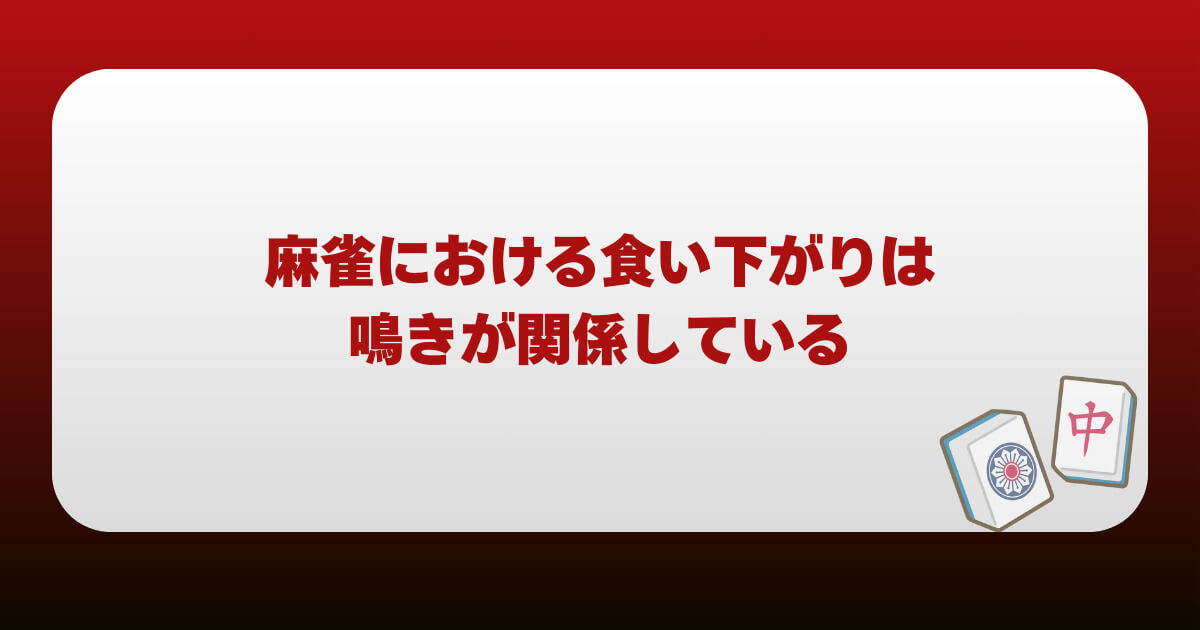
麻雀でときどき耳にする「食い下がり」とは、ポン・チー・カン(明槓)といった鳴きを宣言したときに関わってくる用語です。
鳴いて揃えた牌で役を完成させたときに、本来の翻数から翻数が下がってしまうことを食い下がりといいます。
例えば3翻の役を完成させたとしても、途中で鳴いていた場合は2翻になります。
主に相撲などのスポーツ業界で使われている食い下がるという用語も、低い姿勢を使い相手に対して構える様子から使われているところも考えると、麻雀における「翻数を下げてでもアガリまで持っていく」のは似たような意味であると考えられます。
点数を下げて早く上がれるメリットはあるため、より速度重視の際に使用されるのが食い下がりだと認識しておきましょう。
麻雀の食い下がり役一覧(翻別)
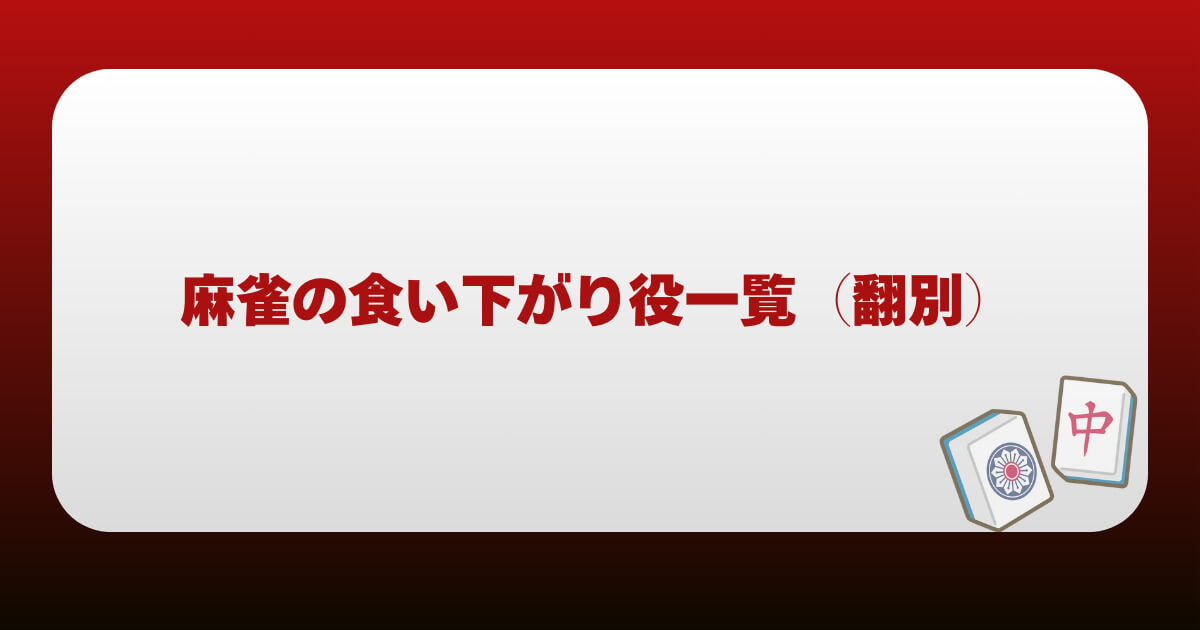
ここからは、翻別で食い下がり役を紹介します。
食い下がりしてしまうことで翻が下がってしまうのも踏まえ、対象となる役をチェックしておきましょう。
一翻
まずは食い下がりで一翻となってしまう役を一覧で見ていきます。
| 役の名前 | 翻(食い下がりなし) | 詳細 |
| 一気通貫(イッキツウカン) | 二翻 | 同じ種類の数牌で123456789の順子を完成させて成立する役 |
| 三色同順(サンショクドウジュン) | 二翻 | 萬子、筒子、索子それぞれで同じ並び順の順子を揃えると成立する役 |
| 混全帯幺九(チャンタ) | 二翻 | 揃えた面子と雀頭すべてに1と9の牌、もしくは字牌が入っていた場合に成立する役 |
二翻
次に、食い下がりで二翻となる役をチェックしてみましょう。
| 役の名前 | 翻(食い下がりなし) | 詳細 |
| 純全帯么九(ジュンチャンタイヤオチュウ) | 三翻 | 揃えた面子と雀頭すべてに老頭牌(1と9の牌)のどちらかが入っていた場合に成立する役 |
| 混一色(ホンイツ) | 三翻 | 萬子、筒子、索子のどれか1種類と字牌だけで揃えると成立する役 |
| 一色三順(イッショクサンジュン) | 三翻 | 同じ種類、かつ同じ数字の順子を3つ揃えると成立する役 |
五翻
最後に、食い下がりで五翻となる役を見ていきます。
| 役の名前 | 翻(食い下がりなし) | 詳細 |
| 清一色(チンイツ) | 六翻 | 萬子、筒子、索子のうちどれか1種類のみで完成させた場合に成立する役 |
麻雀で食い下がりしない役一覧
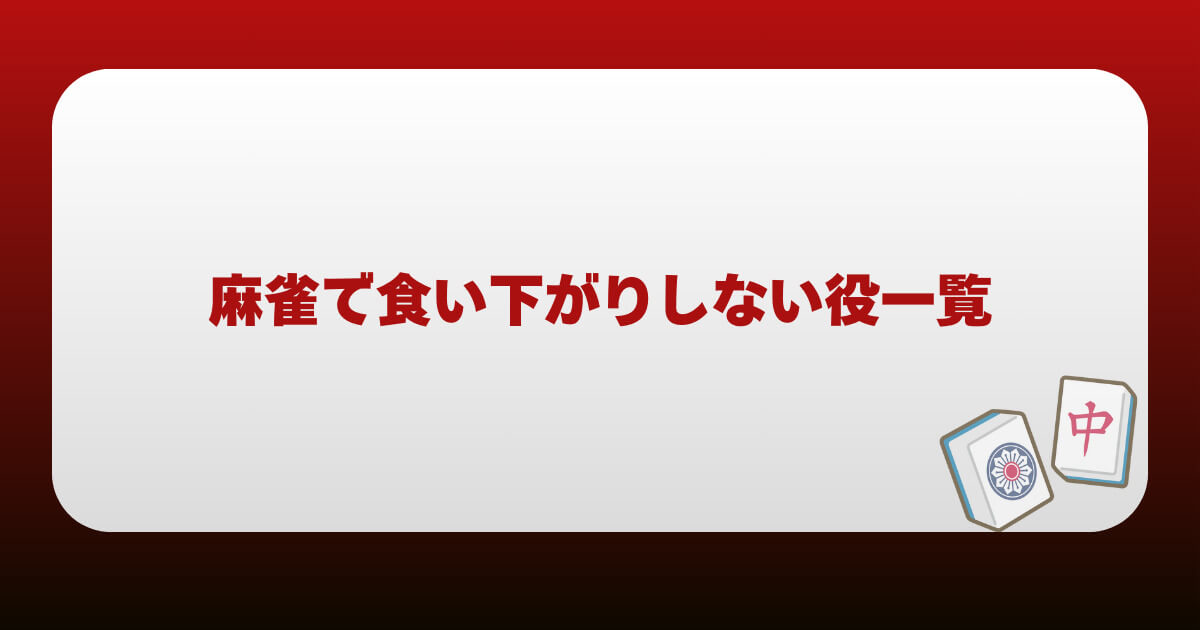
麻雀には、鳴いても食い下がりしない役が存在します。
ここまで紹介した役は食い下がりで翻が下がってしまっていましたが、食い下がりしない役はもちろん、鳴いても翻が下がりません。
ここで紹介する役は副露が使えてかつ点数が下がらない有効的な役なので、余裕があればぜひ覚えておきましょう。
| 役の名前 | 翻 | 詳細 |
| 役牌(ヤクハイ) | 一翻 | 三元牌、自風牌、場風牌のいずれかで3枚揃えると成立する役 |
| 断么九(タンヤオ) | 一翻 | 么九牌(1と9)を一切使わずに手牌を完成させると成立する役 |
| 対々和(トイトイ) | 二翻 | 手牌をすべて刻子(同じ牌3つ)で揃えると成立する役 |
| 三暗刻(サンアンコー) | 二翻 | 暗刻(ツモのみで同じ牌を3つ揃えている状態)を3つ揃えることで成立する役 |
| 海底(ハイテイ) | 一翻 | 局の最後の山からツモった牌でアガリになると成立する役 |
麻雀の食い下がりは鳴いた回数に影響されない
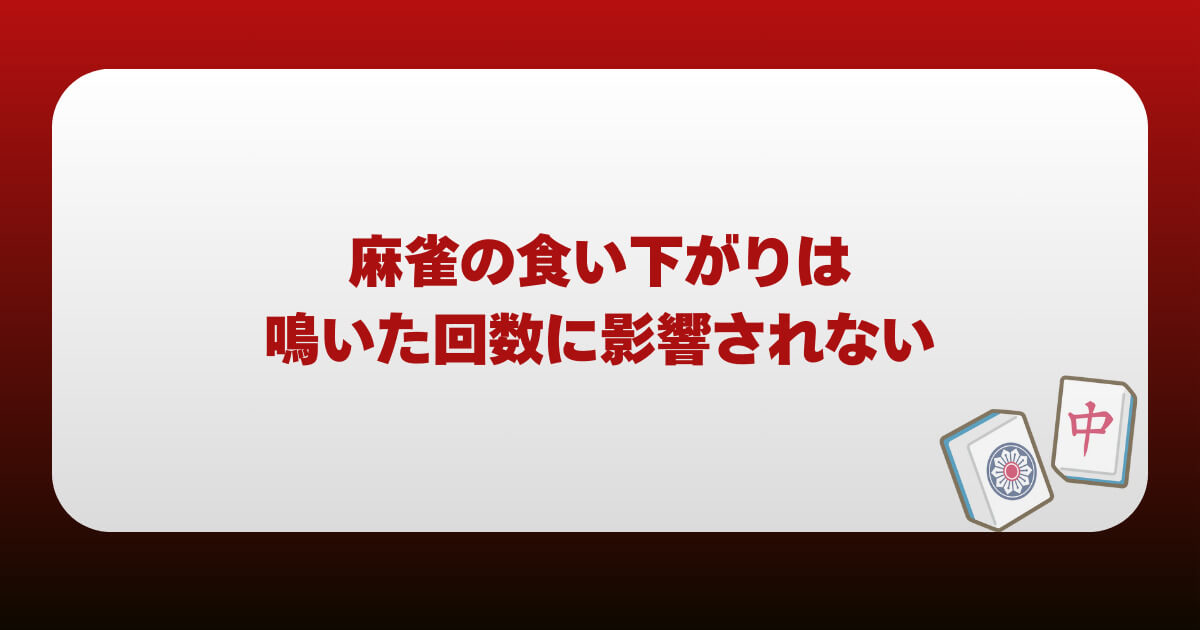
麻雀の食い下がりは鳴くと翻数が下がるというのはここまでで理解できていると考えられますが、食い下がりは鳴いた回数で下がるものではないという点もおさえておくべきです。
食い下がりは基本一翻下がるものであり、2回鳴いたからといって二翻下がるわけではないということです。
例えば混一色はもともと三翻ですが、二回鳴いて完成させたとしても一翻にはならず、二翻として計算されます。
麻雀初心者だと、鳴いた数食い下がりが発生してしまうと思われがちですが、あらためて認識を正しておくことが大切です。
複数の役(複合役)は食い下がりで二翻以上下がることも
食い下がりは鳴いた数に影響されないと紹介しましたが、複合役を揃えていた場合は内容によって二翻以上下がることがあります。
例えば三色同順と純全帯么九を副露して完成させたとします。本来であれば三色同順は二翻であり、純全帯么九は三翻の役なので、合計五翻となります。
しかし、鳴きを使って完成させた場合は食い下がりとなります。
結果として、三色同順は一翻、純全帯么九は二翻で計算されるため、本来五翻で計算される複合役が三翻で計算されてしまう、というわけです。
このように、複数の食い下がり役でアガリとなった場合は翻数が複数下がってしまうことになるので、計算するときは注意しましょう。
麻雀の食い下がりに関するよくある質問
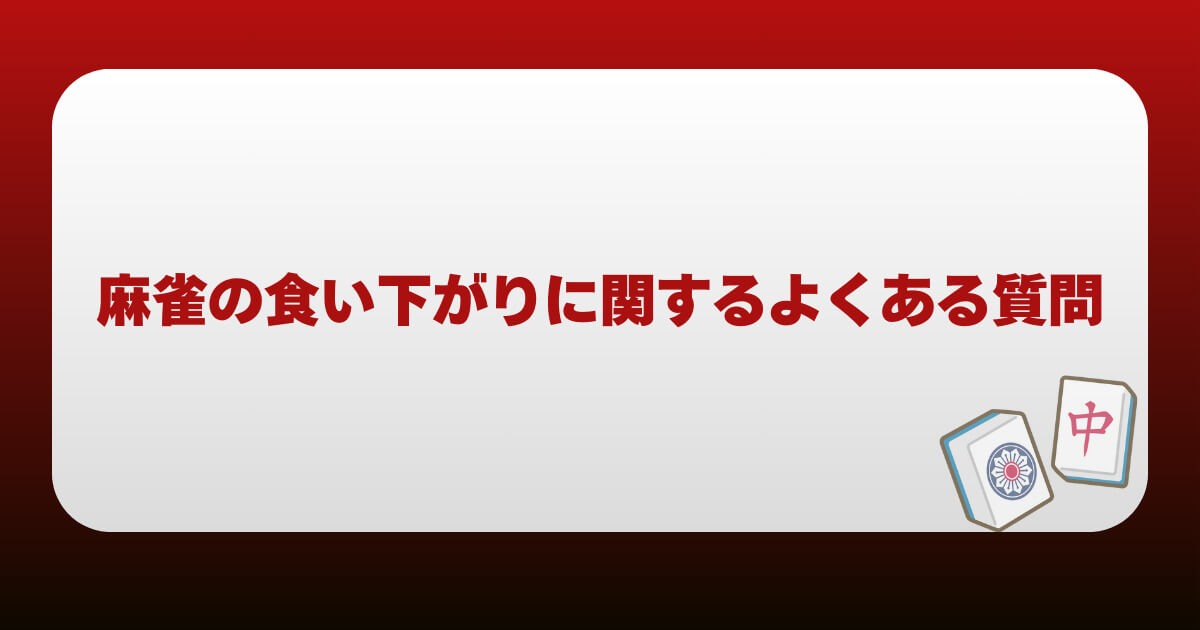
最後に、麻雀の食い下がりに関するよくある質問を見ていきます。
- ・麻雀でポン・チーなどの鳴きを使うと食い下がりになる?
- ・麻雀で食い下がりになってもロンアガリは可能?
- ・麻雀の食い下がりによく出てくる「一翻」「二翻」はどういう意味?
食い下がりについてはやはり、どのタイミングで気をつけなければいけないのかや、食い下がりになっても上がれるのかどうか、といったところが気になるところでしょう。
また、食い下がり時に出てくる◯翻という言葉の意味を知りたい!という方も初心者プレイヤーには多く存在します。
疑問点を解決して、より麻雀を楽しめるようになりましょう。
麻雀でポン・チーなどの鳴きを使うと食い下がりになる?
麻雀の展開のなかで、ポンやチーなどの鳴きを使うと食い下がりになる確率が高くなります。
食い下がりになるかどうかは、揃えようとしている役が関係しているのです。
例えば一気通貫や混一色などは、鳴いてそろえることで食い下がりとなり、一翻下がります。
断么九や三暗刻などは鳴いても食い下がりとならず、翻数は下がりません。
高い点数で上がりたいのであれば、鳴かずに門前のまま立ち回るか、鳴いても食い下がりにならない役を狙っていきましょう。
麻雀で食い下がりになってもロンアガリは可能?
麻雀における食い下がりは、アガリ方には関係してきません。
よって、食い下がりでもロンアガリはもちろん可能です。
ツモアガリも可能であることからも、アガリには食い下がりが影響することはないと考えてよいでしょう。
ただ、食い下がりになっている状態でフリテンになってしまうなど、別の要因で上がれなくなる可能性はあるためこちらは注意です。
麻雀の食い下がりによく出てくる「一翻」「二翻」はどういう意味?
麻雀に登場する翻(ファン、ホン)は、役のランクを示す単位として利用されています。
食い下がりに関係なく、麻雀において翻というのはとても大切です。
役の種類によって翻は変わったり、複数の役が成立していたりしても合計点数は変わります。すべての翻数を合計して点数が決まるため、役が複数できていればそのぶん得点も上がると考えてよいでしょう。
食い下がりが起きると翻数がひとつ下がってしまうので、鳴かずにそろえたときと比べてもらえる点数が下がってしまいます。
そういったデメリットも踏まえ、麻雀で勝ちたいのであれば翻数は必ず把握しておくようにしましょう。
まとめ|食い下がりは麻雀の点数と鳴きに深く関わっている
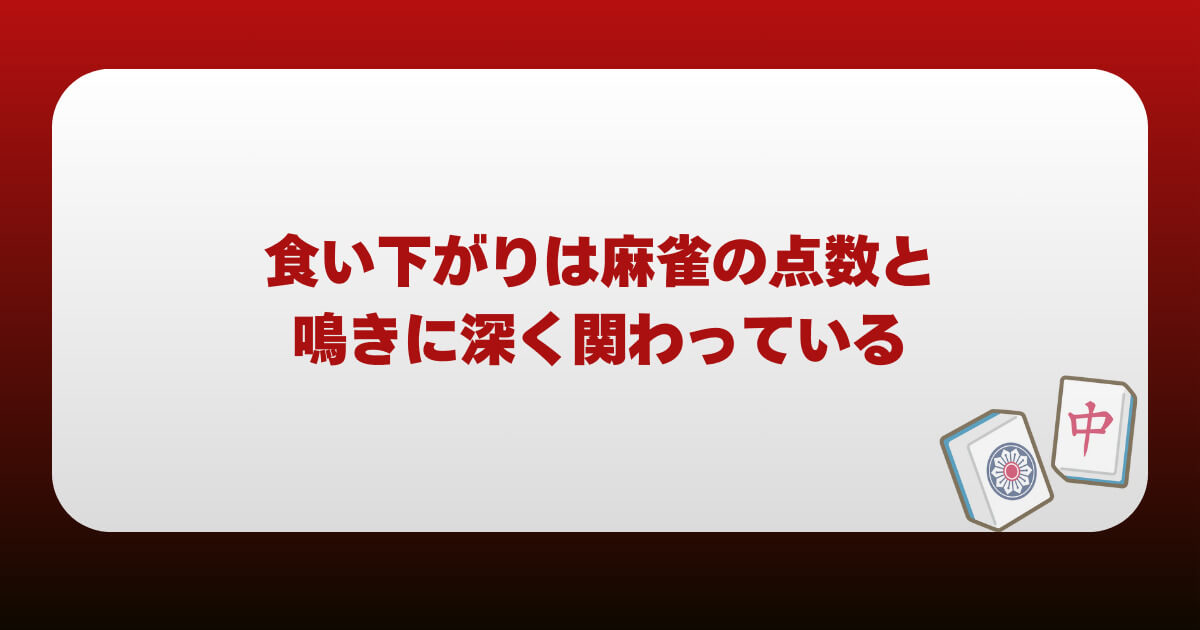
麻雀における食い下がりは、特定の役を鳴き(副露)で完成させると発生します。
もともと二翻だった役なら一翻となり、三翻だった役なら二翻となるように、鳴きで役を作ると一翻下がってしまうのが、役の基本です。
麻雀で登場する翻数は、プレイヤーが得られる点数の計算で使われる重要な数字です。翻数が下がるということは、もらえる点数も下がることを示しています。
ですが、鳴いて牌を揃え、アガリまでの速度を重視するのも麻雀の戦術では有効な手段といえるため、食い下がりを前提にしてでも上がる、というのも視野に入ってくることはあるでしょう。
鳴いても食い下がりにならない役もあるので、そういった役も有効活用するのがおすすめです。
初心者プレイヤーだとなかなか難しい内容かもしれませんが、食い下がりについては覚えておいて損はないといえます。
